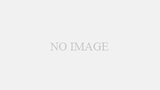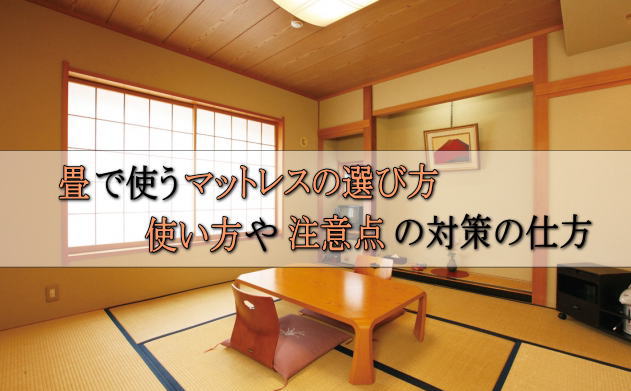畳にマットレスを直置きで使い寝ている人も多いです。
ベッドを使わないデメリットもあるので、どんなマットレスでも和室の畳で問題ない訳ではありません。
しかし、注意点を抑えた選び方や対策によって、畳でマットレスで快適に寝ることができるのですね。
朝の腰痛や背中の痛みに悩まされ、マットレスを使いたいけど、今まで敷布団で床で寝ていたので、ベッドがないから使えないのではと配することも多いです。
この記事では『畳で使うマットレスの選び方』が注意する点や使い方から分かるようになっています。
畳でマットレスで寝るのを検討していたり、すでに実践中の人で使い方を知りたい方はご覧ください。
畳にマットレスを直置きの注意点
畳にマットレスを直置きでベッドなしで使うなら、いくつかデメリットがあります。
そのため、デメリットを解消するように注意をすることが必要となります。
- 湿気が溜まりやすい
- ダニやカビ
- マットレスがずれることがある
- 畳を傷つけないようにする
マットレスは吸収した汗により、底面に湿気が溜まりやすくなっています。
そのため、畳とマットレスの接している部分がしめることで、ダニやカビが発生しやすくあります。
また、寝ている間に滑ってずれたりすることもあるので、対策を検討をした方が良いのですね。
畳マットレスにすのこベッドは使わない
畳にマットレスで寝る時にはすのこベッドは使わないようにしてください。
湿気対策としてマットレスの直置きする時に、安いすのこベッドの上に敷いて寝ることがあります。
しかし、畳で寝ると寝返りなどで自然とずれたりするので、どんどん傷んでいきます。
フローリングやカーペットの上で寝る時の対策として一般的なすのこベッドは畳では使わないように注意をしましょう。
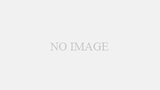
敷きっぱなしでそのままにしない
ベッドで使う時と違い、畳でマットレスで寝るなら敷きっぱなしにはしないようにしましょう。
敷布団に比べるとマットレスはコイルが入ったり、体圧分散などを考慮した設計など、厚みがあり重たいのが多いです。
そのため、敷きっぱなしで使いたい人も多いかと思いますが、壁に立てかけたりなどしてそのままにしないようにしましょう。
毎日行う必要はありませんが、定期的に壁に立てたり、干したりなどのメンテナンスは、敷布団と同様に必要となります。
畳で使うマットレスの選び方
畳で使うマットレスの選び方としてはデメリットの部分を解消できるようにしましょう。
- 底付き感のない厚さ
- 通気性が良い
- 低反発より高反発
余りにも薄いマットレスだと寝た時に体圧がかかることで、へこんで底付き感が感じることがあります。
なぜこれらの3点が必要となるのか、選び方の部分の各項目について詳しく解説していきます。
安易に選ぶと腰痛に悩まされたり失敗することもあるので、どんなマットレスでも良いと考えないようにしましょう。
厚さ8cm以上のマットレス
マットレスを畳で直置きするなら厚さが最低でも8cm以上のを選ぶようにしましょう。
マットレスにも直置きで使えるように厚さがあるのと、敷布団と一緒に使う3cmや5cmぐらいの、トッパーやパッドと呼ばれるのと2種類あります。
寝具に寝た時はからだの重みでマットレスのお尻の部分が沈み、背中のカーブが接地するぐらいのが自分に合うのです。
マットレストッパーやパッドなどの薄いのだと、そのまま直置きで使うものではないので、底付き感がでて腰痛や背中の痛みに悩まされることがあります。
通気性の良いマットレス
畳で使うデメリットの湿気対策として、通気性の良いマットレスを選ぶようにしましょう。
通気性の悪いマットレスを選ぶと、頻繁に壁に立てかけたり、干したりとお手入れの手間が必要となるので、定期的に行うのは面倒な点が多いです。
いざ使うようになると頻繁に行うのは面倒だし、直置きで使うのは厚みもあるので、重たくもあります。
そのため、手間のかからないようにできるだけ通気性の良いマットレスを選ぶのがおすすめです。
ウレタンマットレスに比べると、ポケットコイルやボンネルコイルが入った、スプリングマットレスの方が通気性が良くなってきます。
低反発より高反発
畳でマットレスを使うなら通気性の面からも、低反発より高反発を選ぶのが良いです。
低反発マットレスは体が沈み込むので、素材が圧縮され通気性が悪いです。
そのため、できるだけ高反発を選ぶことで畳で使うデメリットの湿気対策にもなってきます。
但し、日頃の手入れよりも大切なのが自分に合う硬さのマットレスを選べているかの点です。
そのため、体重が45kgの痩せている人だと、高反発は腰が浮いて腰痛になることもあるので、手間よりも快適な睡眠の面から、低反発を選ぶ方が良いです。
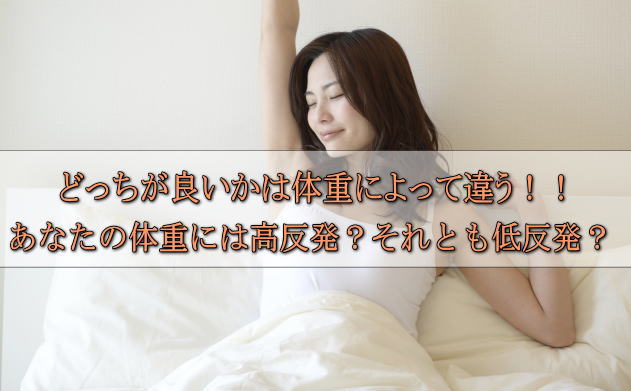
畳にマットレスなしは腰痛になりやすい
畳にマットレスなしでそのまま寝るのは、腰痛や背中の痛みに悩まされやすいので止めるようにしましょう。
フローリングに比べると畳は弾力もあり、体圧がかかることで多少は沈みこんでくれます。
しかし、同様に硬い床で寝るのと同じように、マットレスなしで寝ると腰が浮いた寝姿勢になってしまいます。
そのため、畳にマットレスなしで寝るのを検討している人は、止めるのをおすすめします。
硬さが合わないいと体が沈んだりして、腰痛に悩まされるので、下記の記事では体重別に合う硬さの目安を紹介しているので、参考にしてください。
畳にマットレスの使い方
畳でマットレスの直置きと言っても一般的な使い方と大きく変わることはありません。
但し、湿気によるダニやカビ対策をしたり、畳を傷つけないように心がけないと、マットレスの寿命が短くなったりするので、その点を考えて使うようにしましょう。
- 湿気によるカビ対策をする
- 滑り止めを活用する
畳でのマットレスの使い方は上記の2点を心がけるようにしてください。
畳にマットレスのカビや湿気対策
畳にマットレスを直置きすることによる湿気対策で、下記の対策をするようにしましょう。
- 定期的に干す
- 除湿シートを使う
1週間や2週間おきぐらいで良いので、定期的に陰干しをして風を通すようにしましょう。
また、マットレスを直置きで使用する時ように、除湿シートなども販売されています。
除湿シートの活用は必須ではないものの、使ってく内に湿っているのを感じるようであれば、対策するのを検討するようにしてください。
マットレスだけでなく畳も傷んだり、カビやダニが発生しやすくなるので、防菌・防ダニ対策がされたマットレスを選ぶのがおすすめです。
滑りずれるなら滑り止めを活用
畳にマットレスで寝ていると寝返りや重さなどによっては、敷いてる位置がづれることがあります。
実際に使っていく上でずれた時は、滑り止めを使って対策をするようにしましょう。
畳やカーぺッドで使うのが安いので1,000円ぐらいから販売されていますし、100均のダイソーなどでも震災ようの家具の滑り止めが売られているので活用できます。
そのまま滑っても寝ている分には問題ありませんが、畳を擦ることによってだんだんと痛んでくるようになります。
そのため、実際に寝るようになって万が一滑ってずれるようであれば、滑り止めを使った対策をするようにしましょう。
まとめ:畳にマットレスは手入れの手間を減らす為に通気性
畳にマットレスをベッドなしで使うと言っても、必要以上に注意をしなければいけないことはありません。
しかし、汗を吸収して湿気が床の底面に溜まり、湿気によりカビやダニが発生をしやすくなります。
定期的に陰干しなどをして風通しを良くすることは大切ですが、直置きだと厚さも必要となり重たくもなります。
そのため、通気性の良いマットレスを選ぶことで、頻繁に手入れをする手間を省くようにすると良いのですね。
マットレスの使い方やお手入れについて知りたい方は下記の記事も合わせてご覧ください。